認知症の母と向き合う日々?家族の愛と葛藤とは!?
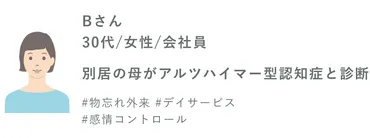
💡 認知症の診断から受診するまでの経緯と、家族の葛藤について詳しく解説します。
💡 認知症の様々な症状や、介護方法、そして家族への影響について紹介します。
💡 認知症の治療法や、介護を支えるための様々なサービスについて解説します。
本日は、認知症の母親を介護する経験についてお話をお伺いします。
母の認知症発覚と診断
まずは、認知症を疑い、受診するまでの経緯についてお伺いします。
公開日:2023/11/14
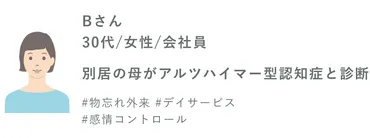
✅ 認知症を疑ってから受診するまでの経緯は、母親が何回も質問を繰り返すようになったことから始まり、友人のアドバイスで物忘れ外来を受診することになった。その後、母親との会話の内容を注意深く観察することで、認知症の可能性を確信し、病院を受診した。
✅ 診断後、薬物治療と並行して脳への刺激として積極的に人と関わる機会を設けている。当初は認知症の集う会に参加し、現在はデイサービスに通うことで家族以外の人と接している。
✅ 認知症と診断された母親との生活は、穏やかに接すること、そして、自分が辛いときは距離を置き、自分の気持ちを優先すること、地域包括センターに頼ることを心がけている。家族が認知症になったことで、母親の行動を直そうとするのではなく、現実を受け入れ、母親に寄り添い、自分を変えることが大変だと実感し、今後も苦労するだろうと述べている。
さらに読む ⇒アスクドクターズ|ネットで医師に相談・Q&A検索出典/画像元: https://www.askdoctors.jp/articles/202954ご自身の体験を通して、認知症の初期症状に気づくことの大切さを感じました。
私は、母が認知症を疑い、物忘れ外来を受診するまでの経緯、そして診断後からの生活について説明します。
母の認知症は、私が気づいたよりも少し前から始まっていた可能性があります。
初期には、同じことを何度も聞いてくることに対して、私は怒ってしまい、母を傷つけていました。
しかし、友人のアドバイスで物忘れ外来を受診し、母がアルツハイマー型認知症と診断されました。
そうか、お母さん、大変だったんやね。でも、こうして話せるのは、すごいことやけん。
認知症と向き合う日々
続いて、認知症と診断されてからの生活についてお伺いします。
公開日:2024/03/28

✅ 認知症の治療は「薬物療法」と「非薬物療法」の2種類に分けられ、薬物療法では認知機能改善薬と行動・心理症状(BPSD)に対する薬が使用されます。
✅ 認知機能改善薬は「アセチルコリンエステラーゼ阻害薬」と「NMDA受容体拮抗剤」の2種類があり、それぞれアセチルコリンの分解を抑えたり、神経細胞の損傷を防いだりする効果があります。
✅ BPSDに対する薬は、睡眠薬、抑肝散などの漢方薬、抗不安薬、抗精神薬、抗てんかん薬などが処方され、本人の精神安定や家族の負担軽減を目的としています。
さらに読む ⇒介護施設・老人ホーム検索のいい介護出典/画像元: https://e-nursingcare.com/guide/dementia/dementia-treatment/drug-therapy/ご自身の体験を通して、介護の大変さを改めて感じました。
診断後は、薬物療法と並行して、デイサービスを利用するなど、積極的に脳に刺激を与える活動を取り入れてきました。
しかし、母の症状は徐々に進行し、以前はできていたことが難しくなってきました。
私は、母の行動を直そうとしたり、理解させようとしたりすることの限界を感じ、母の認知症を受け入れ、寄り添うことの大切さを学びました。
あら、認知症っていろいろあるのね。でも、お医者様もいろいろ考えてくれてるみたいで安心ね。
受け入れと変化
認知症の家族を介護する上で、最も大切なことは何だと思いますか?。

✅ 「48歳で認知症になった母」の作者である美齊津康弘さんは、自身の体験をもとに、ヤングケアラーの現状と課題を漫画で描き、多くの人に知ってもらいたいと語っています。
✅ 特に、ヤングケアラーの孤立を防ぐために、周りの人々の意識改革が重要であり、講演会や音楽制作などを通して啓発活動を行っていくことを表明しています。
✅ 家族の介護に悩む人々に対しては、一人で抱え込まずに専門家に相談すること、そして介護する人の心身の健康を大切にすることの重要性を訴えています。
さらに読む ⇒「知りたい・行きたい」をかなえるニュースメディア|ウォーカープラス出典/画像元: https://www.walkerplus.com/article/1213785/ご自身の経験を通して、家族の心の変化について深く考えさせられました。
母の認知症を受け入れることは、大変な道のりですが、冷静に現状を考え、母の立場に立って穏やかに接することで、私も少しずつ変化してきました。
辛いときは、自分ファーストで考え、地域の包括センターにも頼りながら、この状況と向き合っています。
家族が認知症になると、色々な感情が渦巻きますが、大切なのは、家族の現状を受け入れ、寄り添うことだと思います。
えー、ほんまに大変やけど、お母さんのために頑張ってる姿、かっこいいわ!
介護の始まりと工夫
認知症が進行していく中で、どのような変化がありましたか?。

✅ ワフウフさんの母親であるあーちゃんは、認知症が進行し、新しい病院を受診する際に混乱し、電話の使用方法も忘れてしまい、連絡を取るのも困難な状況でした。
✅ 新しい病院では、あーちゃんは予想外にシャキッとした状態で診察を受け、認知症のテストである「長谷川式認知症スケール」では「姫路城」を「しめじ城」と言い間違えるなど、認知症特有の症状が見られました。
✅ ワフウフさんは、あーちゃんの認知症が進行していることを改めて実感し、ショックを受けながらも、今後の治療方針を決められる良い機会になったと感じています。
さらに読む ⇒ Ameba News アメーバニュース出典/画像元: https://news.ameba.jp/entry/20241027-44268468認知症の進行は、家族にとって大きな試練だと思います。
80歳で脳梗塞を発症した母親が、その後徐々に認知症の症状を呈し、82歳頃に認知症と診断されました。
母子家庭でひとりっ子のため、介護はすべて筆者が担っています。
認知症と診断された後、筆者は母の認知機能の維持を目的に、過去の思い出話や写真集を見せる、日々の出来事を記録する「前の日日記」をつけるなど、様々な工夫を取り入れてきました。
そうか、認知症って進行するんやね。でも、お母さんのためにできることを精一杯やっていくことが大切やけん。
介護の喜びと未来への希望
介護を通して、どのような喜びや希望を感じていますか?。

✅ 榎本睦郎先生は、認知症患者さんと家族が笑顔で過ごせるために、笑いの重要性を強調しています。笑顔は、患者さんへの安心感を与え、問題解決を促進するだけでなく、周辺症状の軽減にも効果があると言われています。
✅ 先生は、認知症介護のコツとして、5つのポイントを挙げられています。「認知症」という言葉を使わずに「もの忘れ」と表現する、患者さんの「できること」に焦点を当てる、患者さんの立場ではなく、少し離れた視点を持つ、役者になりきって笑顔で接する、そして介護サービスを活用して、自分自身の息抜きをする、などです。
✅ 笑顔は、患者さんとの良好な関係を築き、介護をスムーズに行うための重要な要素であると同時に、笑いがもたらす健康効果も紹介されています。ストレス軽減、免疫力向上など、笑いは心身ともに良い影響をもたらすことが研究によって実証されています。
さらに読む ⇒ハルメク365|女性誌部数No.1「ハルメク」公式サイト出典/画像元: https://halmek.co.jp/beauty/c/healthr/2425ご自身の経験を通して、介護の喜びと希望を見出すことの大切さを教えていただきました。
介護は大変ですが、筆者は母の笑顔を見ることが生きがいになっています。
笑わせることを意識したり、スキンケアや歩行をリズムに合わせて行うことで、母の認知機能の維持に努めています。
デイサービスやショートステイを利用することで、筆者自身の精神的なリフレッシュも図っています。
介護は大変ですが、筆者は母と穏やかに過ごせることを願い、今後も母を大切にしていきたいと考えています。
あら、お若いのに介護も大変でしょうけど、笑顔を見れるのは嬉しいことですね。
本日は、貴重な体験談をありがとうございました。
💡 認知症の介護は、大変な道のりですが、家族の愛と支えが大切です。
💡 認知症の家族と向き合うには、専門家のサポートも重要となります。
💡 認知症の家族と一緒に、笑顔で過ごせる未来を目指しましょう。


