戦時歌謡は、本当に『泣く泣く』作られたのか?作曲家たちの葛藤とは!?

💡 戦時歌謡の作曲家たちは、戦争に協力せざるを得なかった状況に置かれていた。
💡 戦後、彼らは「本当に泣く泣く作ったのか」という難しい問題に直面した。
💡 戦時歌謡の歌詞やメロディーに込められた、作曲家たちの思いを探っていく。
それでは、第1章から詳しく見ていきましょう。
戦争と音楽:作曲家の葛藤
戦時歌謡は、戦争を美化したり、国民の士気を高めたりするために作られた歌です。

✅ 童謡「ウミ」が戦争協力作品ではないかという意見について、作詞家の林柳波の経歴や歌詞の内容を検証し、当時の政治状況との関連性を考察している。
✅ 林柳波の妻であるきむ子について、その美貌や個性的な人生を紹介している。彼女は富豪の妻から林柳波の妻、そして事業家へと転身し、時代の変化の中で独自の道を歩んだ人物として描かれている。
✅ 「大正三美人」として知られる林きむ子、柳原白蓮、九条武子の写真とそれぞれの紹介文を通じて、当時の美人の基準や文化、社会状況を垣間見ることができる。
さらに読む ⇒わくわく亭雑記出典/画像元: https://wakuwaku-tei.hatenablog.jp/entry/58611251林きむ子の人生は、まさに時代の変化を表す象徴的なものでしたね。
戦時歌謡の作曲家たちは、戦争に協力せざるを得なかった状況に置かれていました。
戦後、彼らは「本当に泣く泣く作ったのか」という難しい問題に直面しました。
特に、林柳波の童謡「ウミ」が、当時の戦争協力の意図を含んでいたのか、という議論が巻き起こりました。
この議論は、戦時中の時代の状況、林柳波の立場、当時の教育方針などを考慮しながら、慎重に検討する必要があります。
戦争と音楽の関係は、弘田龍太郎や安芸駅など、他の作曲家や場所についても重要な視点を与えてくれます。
現代の視点から、戦時中の音楽がどのように解釈され、どのように理解されるべきなのかという問題について、多角的な考察が必要となります。
え、まじ?林きむ子って、そんなスゴイ人やったんや!
「エール」に見る戦時歌謡
古関裕而の楽曲は、戦争協力という側面と、兵士の心情を表現したという側面があります。
公開日:2020/09/25

✅ 古関裕而は、妻の金子とともに満州への旅行に出かけ、満州の兄妹と会いました。
✅ 満州で旅行中、古関裕而はコロムビア文芸部から「急ぎの作曲があるから神戸で下船しないで東京に上京されたい」という電報を受けました。
✅ 門司で下船後、古関裕而は「進軍の歌」の懸賞募集結果が掲載された『東京日日新聞』を読みました。
さらに読む ⇒婦人公論.jp|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/2610?display=full戦時歌謡の複雑な側面が、改めて浮き彫りになってきましたね。
朝ドラ「エール」では、古関裕而をモデルにした主人公・裕一の戦時中の作曲活動が描かれます。
制作統括の土屋勝裕さんは、戦時中の葛藤や戦後の心情を掘り下げたいと語っています。
戦時歌謡という概念は、軍歌と流行歌を別物として扱う危険性を孕み、軍歌が当時のエンタメと地続きであったこと、そして人々の感情を効果的に動員してしまったという事実を曖昧にする可能性があります。
古関裕而は、満州事変以降、多くの戦時歌謡を作曲し、国民の心を鼓舞する役割を担いました。
しかし、彼の息子である正裕さんは、父親の楽曲は単なる軍歌ではなく、兵士たちの心情に寄り添うものであったと主張します。
特に有名な『露営の歌』は、日中戦争勃発の際に作曲されましたが、古関裕而は実際の戦場を目の当たりにしたことで、戦闘の悲惨さを知り、悲壮感に満ちたメロディーを生み出したとされています。
また、『若鷲の歌』は、当初は勇壮な曲でしたが、古関裕而自身の感性と、予科練生たちの心情が一致したことで、短調で悲しげなメロディーに書き直されました。
へぇー、古関裕而って、満州にも行ってたんや!
「汽車ポッポ」に見る戦時下の歌心
童謡「汽車ポッポ」は、戦時中の歌詞では、兵士を乗せた汽車出発の様子を歌っていたんですね…。

✅ 「汽車ポッポ」の歌詞は戦後改訂され、戦前の「兵隊さんの汽車」では出征する兵士を見送る様子が描かれていた。
✅ 戦前の歌詞では、汽車に乗った兵士に日の丸の旗を振りながら万歳三唱で送り出す様子が描写されている。
✅ 作詞者の富原薫は、静岡県御殿場市の小学校教諭で、陸軍の演習場があり、兵士を送り出す日常風景を歌詞にしたという。
さらに読む ⇒世界の民謡・童謡 WORLDFOLKSONG.COM出典/画像元: https://www.worldfolksong.com/sp/songbook/japan/kisha-poppo.htm戦時の歌は、子どもたちにも戦争の現実を突きつけていたんですね。
童謡「汽車ポッポ」は、戦時中は「兵隊さんの汽車」というタイトルで、歌詞も兵士を乗せた汽車出発の様子を歌ったものでした。
作詞者の富原薫は、戦地へ向かう兵士を乗せた列車が御殿場駅から出発する光景に着想を得て歌詞を書いたそうです。
終戦後にNHKから改作を要請され、現在の歌詞になったものの、富原は「やっぱり兵隊さんの歌なんだよなあ」とつぶやいていたとされています。
歌手矢田稔さんは、戦時中に「兵隊さんの汽車」をレコードでリリースしており、当初の歌詞は兵士を哀れむ気持ちを込めたもので、子どもなりに兵士をねぎらったり励ましたりしなければいけないという義務感があったのではないかと推測されています。
戦時中は、芸術、芸能に携わる多くの人が戦争協力を行い、歌手や作曲家たちも例外ではありませんでした。
矢田さんの師である佐々木すぐるも、戦時中に大ヒットした「兵隊さんよありがとう」を作曲しています。
戦争協力は当時の社会状況において、多くの芸術家にとって避けられないものであったと言えるでしょう。
おばあちゃん!汽車ポッポって、戦時中は全然違う歌やったんかー!
「母もの」が語る戦時下の心情
「母もの」は、戦時下の母の悲しみと強さを、切々と歌い上げています。

✅ 戦時中の母と子を描いた「母もの」は、日中戦争が始まった昭和12年(1937)から、戦局が激化する昭和15年(1940)にかけて多く発表され、多くの人々の共感を呼びました。
✅ 当時の歌謡曲は、表向きは勇ましい軍国調の歌詞で、戦意高揚を促す役割を担っていましたが、実際には、戦死した息子や夫を悼む母の悲しみや、故郷で待つ家族の切ない思いが、メロディーや歌詞に込められていました。
✅ 「軍国の母」「皇国の母」「九段の母」「戦友の母」など、それぞれ異なる設定と心情で歌われた「母もの」は、戦争の残酷さと、それを受け入れる母の強さと悲しみ、そして家族の絆を表現し、戦時下の人々の心を強く揺さぶった楽曲として、今日でも語り継がれています。
さらに読む ⇒BIGLOBEニュース出典/画像元: https://news.biglobe.ne.jp/trend/1101/fjk_241101_8233771433.html戦時歌謡は、ただ戦争を美化するだけでなく、人間の心の奥底にある深い悲しみも表現していたんですね。
昭和歌謡史における『母もの』は、日中戦争下の厳しい時代に生まれた歌であり、祖国のために戦死した息子を悼む母の心情を描いています。
美ち奴の『軍国の母』は、勇ましい歌詞と悲壮感漂う旋律で、当時の世相を反映しています。
歌詞は「建て前」として勇ましい言葉を並べていますが、作曲家の古賀政男は、母の本音である悲しみを表現するために、レクイエムのような旋律を付け加えました。
一方、音丸の『皇国の母』は、夫の戦死を乗り越え、息子を立派に育てていく強い母の決意を描いています。
これらの『母もの』は、戦死した家族を悼む遺族への慰めの歌であり、昭和歌謡が当時の社会状況を反映したものであることを示しています。
また、表面的な勇ましさと、内面にある悲しみという対比が、戦時下の国民の複雑な心情を浮き彫りにしています。
お母さん、ホンマに大変やったんやなぁ。
「露営の歌」と作曲家の足跡
「露営の歌」は、戦争の悲惨さを強く感じさせる楽曲ですね。
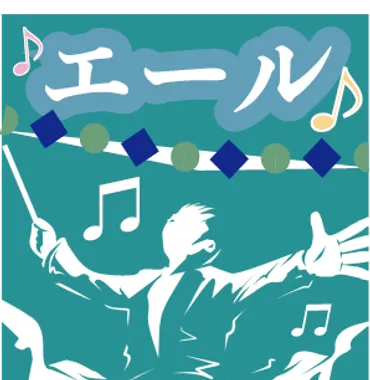
✅ この記事では、NHK連続テレビ小説「エール」に登場する音楽、歌をまとめ、ドラマの内容と関連付けて紹介しています。
✅ 特に主人公・古山裕一のモデル人物である作曲家・古関裕而の作曲した楽曲に焦点を当て、ドラマの進捗に合わせた随時追記を予定している点が特徴です。
✅ また、ドラマオリジナル楽曲と思われるものには「※」マークを付けて区別し、各楽曲の詳細情報や関連エピソードを分かりやすく解説しています。
さらに読む ⇒ロケTV |出典/画像元: https://locatv.com/yell-songs/作曲家の戦時中の足跡を追うことで、戦争の悲劇がより深く理解できます。
「露営の歌」の作詞者、藪内清の記念碑建立を記念した写真が公開された。
写真は1938年の除幕式で、藪内と作曲者の古関裕而らが写っている。
記事では、古関裕而が数々の戦時歌謡を作曲した戦中の足跡をたどり、盧溝橋事件から日中戦争へ拡大していく中で、古関が戦時歌謡作曲に携わるようになった経緯を説明している。
古関裕而って、戦時歌謡ばっかり作ってたんかー。
戦時歌謡を通して、戦争と音楽の関係、そして人々の心情について深く考えさせられました。
💡 戦時歌謡の歌詞やメロディーには、作曲家の葛藤や当時の社会状況が反映されている。
💡 戦時歌謡は、単なる軍歌ではなく、兵士たちの心情や母の悲しみ、家族の絆などを表現した歌でもあった。
💡 戦時歌謡は、現代においても、戦争の記憶や教訓を伝える重要な資料となっている。


