『光る君へ』まひろは一体どんな物語を書いたのか?紫式部誕生秘話とは!?

💡 平安時代を舞台にした、紫式部の生涯を描いた物語
💡 藤原道長と紫式部の複雑な関係が物語の鍵を握る
💡 歴史とフィクションが織りなす、壮大な人間ドラマ
それでは、第一章「物語の誕生と献上」から見ていきましょう。
物語の誕生と献上
この章では、まひろが物語を書くに至るまでの経緯と、藤原道長の策略が描かれています。

✅ 興福寺の僧侶が朝廷に要求を突きつけ、道長は事の収拾に奔走する。
✅ 一方、まひろは物語を書き進め、宮中で話題になるが、一条天皇と彰子の関係は深まらず、道長の望む彰子の懐妊も叶わない。
✅ 都で病や火事などの不吉な出来事が続き、道長は決断を迫られる中、天皇がまひろを訪ねてくる。
さらに読む ⇒富裕層向け資産防衛メディア | ゴールドオンライン出典/画像元: https://gentosha-go.com/articles/-/63386まひろが書いた物語が、一条天皇にどのように受け止められたのか、興味深いですね。
1005年(寛弘2年)12月29日、藤原彰子に仕えることになったまひろは、「藤式部」という呼び名を授かり、物語を書くための小部屋を与えられます。
しかし、周りの女房達からは反感を抱かれ、なかなか執筆に集中できませんでした。
まひろは藤原道長に実家で執筆したいと願い出ますが、藤原道長はそれを許さず、一条天皇の気が変わらないうちに物語を完成させろと命じます。
藤原道長は、まひろの物語で一条天皇を藤壺に通わせることを「最後の賭け」と位置づけていました。
1006年(寛弘3年)5月、まひろは「光る君」を主人公にした物語を書き上げ、藤壺を訪れます。
藤原彰子は物語に興味を示し、主人公の名前を尋ねます。
まひろは「光る君でございます」と答え、物語を一条天皇に献上します。
一条天皇は物語に心を捉えられ、まひろにその理由を尋ねます。
まひろはかな文字で書いたことが理由だと答え、一条天皇はまひろの才能に感心します。
え、マジ!?物語で天皇を操るって、すごい戦略やんな!
脅迫と過去の記憶
この章では、藤原道長と興福寺との対立が描かれます。

✅ 藤原道長は、興福寺が源頼親の解任を求めた事件で、頼親を守り、興福寺の要求を退けた。
✅ 道長は、興福寺が藤原氏の氏寺であり、頼親が自分自身の近侍であることから、苦渋の選択を迫られた。
✅ 道長の決断は、興福寺の大衆が都に押し寄せ、八省院に押しかけた強訴に対し、道長が許すことができず、頼親側に立ったことによるものと思われる。
さらに読む ⇒よろず〜ニュース出典/画像元: https://yorozoonews.jp/article/15419493興福寺の脅迫に対し、藤原道長が毅然とした態度を見せたのは、さすがですね。
藤原道長は、興福寺の僧兵3000人の脅迫に毅然と立ち向かいます。
物語の執筆に集中できないまひろは、内裏で周りの女房から酷評された過去を思い出します。
まひろは、過去の悪口を皮肉で返し、その記憶は彼女の物語にも反映されていると推測されます。
33話でまひろが読んだ「雨夜の品定め」は、源氏物語の「帚木」の巻に描かれた場面と考えられます。
この場面は、光源氏が雨の夜に恋愛談義を聞くシーンであり、まひろの経験が物語に投影されている可能性があります。
道長さん、かっこよすぎ!あの僧兵3000人相手にビビらんとか、惚れちゃうわ!
運命の交錯
この章では、まひろと道長の関係、そして倫子の願いが明らかになります。

✅ 道長との関係を倫子に打ち明けられたまひろは、二人の過去を告白し、倫子からある願いを託されます。
✅ まひろは『源氏物語』に興味を持った見知らぬ娘と出会い、自身の作品に対する新たな意見を聞きます。
✅ 道長は周囲の人々の死を経験し、自らの死期を悟り、最後の決断を下します。まひろのもとに道長の危篤の知らせが届き、物語はクライマックスを迎えます。
さらに読む ⇒デイリースポーツ online出典/画像元: https://www.daily.co.jp/leisure/kansai/2024/12/09/0018428572.shtmlまひろは、道長との過去を告白し、倫子からある願いを託されるという展開は、ドラマティックで感動的でした。
2024年NHK大河ドラマ「光る君へ」最終回(第48話)では、藤原道長、倫子、そして主人公まひろの運命が交差し、平安時代の宮廷で繰り広げられた波乱万丈な人生が幕を下ろします。
まひろは源倫子にこれまでの自分の人生について語り、道長は倫子に「何を話していたのか」と尋ねますが、倫子は「ただの昔話よ」と受け流します。
道長の末娘・嬉子は東宮・敦良親王に嫁ぎ、皇子・親仁親王を出産しますが、わずか二日後に亡くなります。
親仁親王は、嬉子の姉である太皇太后・藤原彰子のもとで育てられ、まひろの娘である賢子が乳母に任命されます。
万寿4年(1027年)には、道長の時代を築いた公卿たちが次々と姿を消し、道長の息子たちが新たな政の中心に立ち始めます。
道長と倫子の娘である妍子が亡くなり、道長は病に倒れ、その生涯を閉じます。
倫子ちゃんの願いって、一体何だったんやろ?まひろちゃん、頑張って!
旅立ちと新たな章
この章では、まひろの旅立ちと新たな章が描かれます。
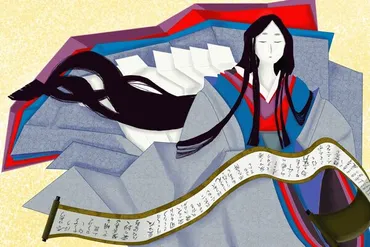
✅ 今回の放送では、紫式部ことまひろが政治的な発言をし、父である藤原為時を驚かせたことが大きな見どころです。
✅ まひろは、三郎との関係を断ち切るため、左大臣家との関係を深め、父の政治的な立場を強化することを決意しました。
✅ 三郎が母の仇である道兼の弟だと知り、過去のトラウマと向き合い、三郎への想いを断ち切る決意をしたことが、まひろの行動の変化の背景にあります。
さらに読む ⇒JBpress (ジェイビープレス) | リアルな知性で世界に勝つ出典/画像元: https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/79458まひろが三郎との関係を断ち切り、父である藤原為時を驚かせたのは、彼女の成長を感じました。
道長が亡くなった後、まひろは乙丸という従者を連れて再び旅に出る決意をします。
旅立つ前、まひろは娘の賢子に自分がこれまで詠んだ歌をひとつの歌集にまとめたものを手渡します。
その歌集の名は『紫式部集』。
まひろは過去の経験や思い出を振り返りながら、自分なりの答えを見つけようとしていました。
最終回では、これまでの登場人物たちの運命が交差し、特に源倫子や藤原道長、まひろの心情が深く描かれる場面が期待されます。
権力争いや家族の絆、そして詩歌の美しさが巧みに絡み合い、平安時代の宮廷社会が鮮やかに描かれるでしょう。
道長の娘たちの悲劇的な運命や、次世代を担う人物たちの登場も見逃せないポイントです。
まひろちゃん、旅立つって!?ちょ、待っ!私も一緒に行きたい!
権力争いの渦中
この章では、道長の権力争いが激化する様子が描かれます。
公開日:2024/11/03

✅ 道長は三条天皇との権力闘争の中で、三条天皇が姸子を中宮にした後に娍子を皇后にすると宣言された。これは道長にとって特大ブーメランであり、一帝二后という前例のない事態を引き起こした。
✅ 三条天皇による一帝二后は、道長が娘の彰子を中宮とした際に用いた理論武装とは異なり、単に先例があるからという理由で実行された。
✅ 娍子を皇后にするための理由付けとして、娍子の亡父済時に太政大臣の位を贈ることで体裁を整えた。
さらに読む ⇒サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/hobby/1206527道長は、三条天皇との権力闘争の中で、一帝二后という前例のない事態を引き起こしました。
『光る君へ』42話では、道長の三男・顕信の突然の出家という衝撃的な出来事が描かれる。
明子は息子を案じ、道長も深い傷を負うが、左大臣としての責務は重く、心を癒す暇はない。
三条帝は道長の次女・姸子を中宮とし、彰子を皇太后とすることを提案する。
これは、道長にとってありがたい話だが、帝の隠された目的があるのではないかと疑心暗鬼になる。
帝は、自身の妻である娍子を皇后にしたいという願いを表明する。
道長は、大納言の息女が皇后となった例がないことを理由に抵抗するが、帝は亡き済時に右大臣の称号を贈ることで、立后を実現しようとする。
道長は、四納言たちと対策を練り、娍子の立后の儀に姸子の中宮参入をぶつけるというえげつない策を立てる。
帝は、両方の儀式に公卿たちが参列できるよう、時間をずらすことを提案する。
しかし、立后の儀式にはほとんどの公卿が欠席し、そこに現れたのは、大納言・実資だった。
実資は大臣らの不在に戸惑いながらも、儀式の指揮を執る。
実資の日記『小右記』には、儒教の経典『礼記』の言葉「天に二日なし、土に二主なし」が記されていた。
道長さん、やっぱりすごい!でも、一帝二后って、ちょっとワケわかんないよね!
以上、『光る君へ』の物語を振り返ってみました。
💡 紫式部の物語は、藤原道長という権力者の策略と、まひろ自身の強い意志が交錯する物語
💡 物語を通して、平安時代の政治や文化、そして人々の生き様を感じることができる
💡 『光る君へ』は歴史とフィクションが融合した、見応えのある作品


