宝塚歌劇、知っとる?(疑問形で終わる)宝塚歌劇とは!!?

💡 宝塚歌劇は、阪急電鉄の創設者である小林一三によって創設された、女性のみで構成される劇団です。
💡 宝塚歌劇には、男役と娘役の組み合わせが特徴的で、華やかな舞台と同時に、礼儀作法や社会人としての品格を重んじる教育が行われています。
💡 宝塚歌劇は、舞台芸術としてだけでなく、社会文化現象としても注目されています。
それでは、宝塚歌劇の歴史や魅力について詳しく見ていきましょう。
宝塚歌劇の歴史と魅力
宝塚歌劇の歴史は、小林一三の革新的なアイデアから始まったんですね。
公開日:2023/07/01

✅ 阪急電鉄の前身である箕面有馬電気軌道は、沿線人口が少ないため乗客を増やすため、経営トップ小林一三は沿線の住宅分譲と大衆娯楽施設の開設という戦略を打ち出しました。
✅ 宝塚新温泉の隣に増設したパラダイスの室内プールが失敗に終わったことから、小林一三はプールを改造して少女に唱歌を歌わせ、劇を演じさせるというアイデアを思いつき、これが宝塚歌劇の始まりとなりました。
✅ 小林一三は単なる思い付きではなく、歌が好きな良家の少女を募集し、水準以上の俸給を支払うなど、人材育成にも力を入れていました。幼少期からの芝居好きが歌劇立ち上げで開花し、宝塚歌劇団は「清く、正しく、美しく」をモットーに、未婚女性のみ舞台に立てるという独自のスタイルを守り続け、100年間存続してきました。
さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/views/b03903/宝塚歌劇は、単なる舞台芸術ではなく、社会に貢献する文化として発展してきたことがよくわかります。
宝塚歌劇は、阪急電鉄の創設者である小林一三によって1914年に創設された、女性のみで構成される劇団です。
当初は鉄道の乗客誘致を目的とした「宝塚新温泉」の室内プールを改造して始まりました。
小林一三は「清く正しく美しく」というモットーを掲げ、華やかな舞台と同時に、礼儀作法や社会人としての品格を重んじる教育を行いました。
宝塚歌劇は、男性役の「男役」と女性役の「娘役」によるコンビネーションが特徴です。
現在、花・月・雪・星・宙の5組と専科があり、各組には約80名のタカラジェンヌが所属しています。
宝塚音楽学校を卒業した生徒が、毎年初舞台公演を経て配属されます。
宝塚歌劇は、桃太郎を題材にした『ドンブラコ』で幕を開け、1世紀を超えてオリジナル作品や海外作品など幅広いジャンルの作品を上演しています。
物語の世界観を楽しめるお芝居と、華やかなショーの二本立てが一般的で、中には一本物のお芝居にショーが付いている公演もあります。
宝塚歌劇のショーは、「ラインダンス」「大きな羽根飾り」や「大階段のパレード」など、歌とダンスを中心とした豪華絢爛な演出が魅力です。
舞台装置や衣装、照明、小道具に至るまで、細部にこだわった空間演出が施されています。
宝塚歌劇の専属オーケストラである「宝塚クリエイティブアーツ」が、公演の生演奏を担当しており、クラシックからジャズ、ロックまで、様々なジャンルの音楽を演奏しています。
へぇ~、宝塚ってそんな歴史があったんや!意外やわ~
宝塚歌劇の観劇マナー
観劇マナーは、他の劇場と比べて特に厳しいものがあるんですね。

✅ 宝塚歌劇の「出待ち」「入待ち」を安全に楽しむためのルールやマナーについて解説しています。
✅ 出待ちには「ガード」と「ギャラリー」の2種類があり、ガードはファンクラブに入会して手紙を渡したり、会話したりすることができますが、ギャラリーは写真撮影のみ可能です。
✅ 出待ちをする際は、通行人の邪魔にならないように、また、劇場の出入り口以外での場所での声かけは控えるなど、最低限のマナーを守ることが大切です。
さらに読む ⇒ 宝塚市の神社やカフェなど観光スポットを伝えるブログ出典/画像元: https://takarakko.com/waiting-757宝塚歌劇の観劇マナーは、ファンと劇場の関係を良好に保つために重要なものだと感じました。
宝塚歌劇の観劇マナーは、他の劇場と同じように基本的なマナーを守れば問題ありません。
しかし、入り出待ちに関しては、宝塚ファンの中で暗黙のルールが存在し、このマナーが宝塚の秩序を支えていると言えます。
当日券に並ぶ際は、劇場の指示に従い、通行人に迷惑をかけないよう並びましょう。
また、徹夜で並ぶことは避け、寝袋にくるまる際は、劇団に迷惑がかからないよう注意が必要です。
当日券は枚数に限りがあり、横入りや抜かしは厳禁です。
入り待ち・出待ちでは、ジェンヌさんの個人の会(非公式ファンクラブ)が劇場前で待機しており、会員よりも前に出てジェンヌさんを待つことは禁止されています。
また、大声でジェンヌさんに声をかけるのも控えるべきです。
写真を撮るときはフラッシュを焚かないように注意しましょう。
ジェンヌさんの目を傷つけてしまう可能性があります。
街でジェンヌさんを見かけても、むやみに話しかけることは避け、プライベートを尊重しましょう。
宝塚って、なんか色々ルールあるんやね~!?めんどくさいけど、ジェンヌさんとの距離近くなるなら、頑張るわ!
宝塚歌劇の「入り待ち」「出待ち」のマナー
宝塚歌劇団では、ファンとの交流が公式化されているとは驚きです。

✅ 宝塚歌劇団では、ファンの「入り待ち」「出待ち」が公式化されており、スターの出勤時にファンが楽屋口付近で待ち、スターはファンレターやプレゼントを受け取ったり、一言あいさつをするなど、ファンとの交流をしています。
✅ スターのファンクラブを中心にブロック分けされ、整列して待ちます。スターは出勤前に自分のファンクラブのもとへ行き、ファンと交流を行います。
✅ 出待ちや入り待ちでは、舞台メイクではなく薄いメイクをしていることが多いので、ファンはスターの素顔を見ることができる貴重な時間となっています。
さらに読む ⇒ あいり゛s Ownd出典/画像元: https://zuka-lovepear.amebaownd.com/posts/5269677/ファンとスターの距離が近いのも、宝塚歌劇の魅力の一つですね。
宝塚歌劇の「入り待ち」「出待ち」は、出演者を応援するファンが劇場周辺で行う活動です。
誰でも参加できますが、ファンクラブ会員と一般のギャラリーでは、できることやできないことが異なります。
ファンクラブ会員は、特定の生徒を応援する集団で、服装、並び方、できることなどにルールがあります。
生徒に直接手紙を手渡ししたり、お見送りなどの声かけをしたりできますが、写真撮影や複数の生徒の掛け持ちは禁止されています。
一般のギャラリーは、誰でも参加できますが、生徒からの目線やファンサービスはありません。
写真撮影は可能ですが、フラッシュ撮影は禁止です。
「入り待ち」「出待ち」をする際には、周囲に迷惑をかけないように、ルールを守って楽しみましょう。
えー!入り待ちとか出待ちって、宝塚歌劇では公式なんや!?スゴイ!
宝塚歌劇の専門家による解説
専門家の視点から見た宝塚歌劇は、より深く理解することができます。
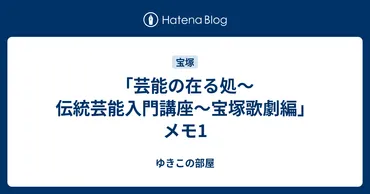
✅ この記事は、ローム シアター京都主催の「芸能の在る処~ 伝統芸能 入門講座~ 宝塚歌劇 編」の内容をまとめたものです。
✅ 講座では、木ノ下歌舞伎の演出家・木ノ下裕一さんが案内役となり、宝塚歌劇の演出家・上田久美子さんと、宝塚歌劇研究者の松本俊樹さんをゲストに迎えています。
✅ テーマは「劇場」と「レパートリー」という二つの視点から宝塚歌劇を考察し、宝塚歌劇が持つ「唯一無二」という概念を検証することです。また、宝塚歌劇の歴史、演出、そして社会における位置づけについて、それぞれの専門家の視点から解説しています。
さらに読む ⇒ゆきこの部屋出典/画像元: https://yukiko221b.hatenablog.com/entry/2022/12/04/194119今回の講座では、宝塚歌劇の演出や歴史、社会における位置づけについて、様々な角度から考察することができました。
「伝統芸能入門講座〜芸能の在る処〜」の最終回は、宝塚歌劇をテーマに、脚本・演出家の上田久美子氏と近代日本演劇史研究者の松本俊樹氏を招き、宝塚歌劇の歩みと魅力、上田作品の独創性について語り合った。
松本氏のレクチャーでは、宝塚歌劇団の成り立ちから、レヴュー導入による大衆化、劇場構造の特徴、スターシステムと専用劇場の関係などを、同時代の少女歌劇や宝塚の劇場構造、レパートリーの特徴をひもときながら解説した。
宝塚歌劇団は、阪急電鉄の創設者である小林一三によって1913年に「宝塚唱歌隊」として誕生し、1914年に宝塚新温泉の集客の一環として初公演を行った。
当初は、少女で構成され、家庭本位の娯楽であったが、1919年に宝塚音楽歌劇学校を設立し、小林は「少女歌劇を元にした゛国民劇゛の確立」を目指した。
1924年に完成した宝塚大劇場(初代)では、フランスで流行していたレヴューが日本で初めて導入され、「モン・パリ」や「パリゼット」などのヒット作が誕生した。
宝塚が自前の劇場を有していることで、舞台の間口が広く奥行きが狭い、銀橋と呼ばれるエプロンステージが存在するなど、劇団の特性を活かした公演が可能になった。
これらの特徴は、宝塚のレヴューやミュージカルを特徴付ける要素となっている。
松本氏は、宝塚の特徴は、当時の流行を積極的に取り入れた結果であり、決して最初から唯一無二の存在ではなかったと指摘した。
宝塚って、ただの舞台劇とかじゃないんやね~!?深い!
宝塚歌劇の歴史
宝塚歌劇の歴史は、まさに舞台芸術の進化の歴史ですね。
公開日:2021/10/26

✅ 宝塚歌劇団の花組と月組は今年で創立100周年を迎えます。
✅ 1914年の初公演時は組分けがなく、17人のみでスタートしました。
✅ 現在では団員が400人以上おり、花・月・雪・星・宙の5組と専科に分かれています。
さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20211026/ddm/003/070/065000c創設から100年以上続く宝塚歌劇は、時代の変化と共に進化を続けてきたことがわかります。
宝塚歌劇は1914年4月1日に宝塚新温泉の余興として第一回公演が行われました。
当初は室内プールを改造したパラダイス劇場で上演され、好評を得て年4回の公演を実施するようになりました。
観客数の増加に伴い、1921年にはパラダイス劇場と公会堂劇場に分かれて公演を行う二部制が導入され、花組と月組が誕生しました。
1924年には4000人収容の旧・宝塚大劇場が完成し、月・花組合同のこけら落とし公演が開催されました。
同年7月には雪組が発足し、翌年には花・月・雪の3組が月交代で常時公演を行うようになりました。
1927年には日本初のレビュー『モン・パリ<吾が巴里よ>』が上演され、舞台芸術に新たな息吹をもたらしました。
続く1930年の『パリゼット』ではタップダンスが日本で初めて舞台に登場し話題となりました。
その主題歌「すみれの花咲く頃」「おお宝塚」は、のちに宝塚歌劇を象徴する歌となりました。
1934年には旧・東京宝塚劇場が日比谷に誕生し、月組によるレビュー『花詩集』ほか数作品でこけら落とし公演が行われました。
東京の常設劇場開場に向けて、前年1933年7月には新しく星組が誕生しました。
1938年には初の海外公演としてドイツ・イタリア公演が行われ、「日独伊親善芸術使節団」として神戸港を出発、ドイツ、ポーランド、イタリアの3ヶ国で公演しました。
翌年にはアメリカ公演も実施され、海外で日本情緒を随所に表現した作品を上演し、国際親善に貢献しました。
しかし1944年には本土への空襲が始まり、宝塚大劇場と東京宝塚劇場を含む全国19劇場が閉鎖されました。
宝塚大劇場と周辺の施設は海軍に接収され、生徒たちは各地で慰問公演を行いました。
終戦後、1946年4月に宝塚大劇場での公演が再開され、翌年4月には東京の有楽町・日本劇場で公演が再開されました。
1950年代に入ると、国際的な活動が再開され、海外の映画祭や日伊合作映画「蝶々夫人」の撮影に参加しました。
1955年には第一回ハワイ公演を開催し、同年には長らくアーニー・パイル劇場と改称し接収されていた旧・東京宝塚劇場での公演が、『虞美人』で再開を果たしました。
1957年には宝塚歌劇の創設者小林一三が逝去しました。
宝塚歌劇は、1964年に50周年を迎え、東京オリンピックの開催、東海道新幹線の東京~新大阪間開通に活気づく中、新たな挑戦として初の海外ミュージカル『オクラホマ!』を上演しました。
以降、『ウェストサイド物語』『回転木馬』などを上演し、高く評価されました。
1970年には大阪でアジア初の国際博、日本万国博覧会(EXPO’70)が開催され、宝塚大劇場では会期に合わせてレビュー『タカラヅカEXPO’70』を上演しました。
宝塚って、もう100年以上も続いてるんや!すごい!
宝塚歌劇は、歴史と伝統、そして革新性を兼ね備えた、魅力的な舞台芸術です。
💡 宝塚歌劇は、阪急電鉄創業者の小林一三によって創設されました。
💡 宝塚歌劇は、女性のみで構成される劇団で、「清く、正しく、美しく」をモットーにしています。
💡 宝塚歌劇は、華やかな舞台と、ファンとの交流など、独特の魅力を持っています。


