くるり:オリジナルメンバー再集結!新作アルバム&映画『くるりのえいが』はどんな内容?オリジナルメンバー再集結による音楽創作と、ドキュメンタリー映画『くるりのえいが』の公開情報
くるりが20年ぶりに再集結!アルバム制作の裏側を追ったドキュメンタリー映画「くるりのえいが」が10月13日公開!スタジオでのセッション、メンバーインタビューで、音楽誕生の奇跡とバンドの深淵に触れる。
京都音楽博覧会:コロナ禍を経て進化を遂げる
音博オンライン開催で岸田繁さんは何を「種まき」したのか?
制作活動への集中
コロナ禍でオンライン形式で開催された京都音楽博覧会は、新しい試みとして注目を集めました。

✅ くるりの主催するライブイベント「京都音楽博覧会2020」が、オンライン形式で開催され、岸田繁楽団の演奏会とくるりのライブが配信された。
✅ 岸田繁楽団は、アコースティックギター、弦楽器、ゲストボーカルなどを交え、様々な楽曲を演奏し、温かなアンサンブルを奏でた。
✅ くるりのライブでは、新旧織り交ぜた楽曲を演奏し、新曲「益荒男さん」と「潮風のアリア」が初披露された。また、トークは控え、集中して演奏するスタイルで、バンドの力強さを示した。
さらに読む ⇒ナタリーポップカルチャーのニュースサイト出典/画像元: https://natalie.mu/music/news/397391オンライン開催を通して、くるりは制作活動に集中し、新たな音楽を生み出したと言えるでしょう。
3年ぶりの現地開催が楽しみですね。
くるり・岸田繁さんへのインタビューから、京都音楽博覧会(音博)のオンライン開催(2020年、2021年)と、3年ぶりの現地開催(2023年)についてまとめます。
コロナ禍でのオンライン開催は、岸田さんにとって「種まき」の期間であったと語られています。
ライブ活動が困難な状況下で、制作活動に集中し、原点回帰ともいえる時間を過ごしたとのことです。
特に、2020年のトレーラームービーで紹介された「岸田繁楽団」は、自身の音楽活動の背景やアイデンティティを伝える試みとして、岸田さんにとって貴重な作品となりました。
オンライン開催を通して、岸田さんは制作活動における時間を大切にすることの重要性を感じ、楽曲制作への取り組み方がより深まったことを明かしています。
長期間向き合うことで、より深みのある作品が生まれると実感しているそうです。
2023年は3年ぶりの現地開催となる音博。
岸田さんは、「初心にかえってエイッとやってみたい」と意気込みを語っています。
オンライン開催で試みられた新たな試みも踏まえ、進化した音博が期待されます。
オンラインでライブって、私もやってみたいわ!でも、おばあちゃんなんて、みんな興味ないやろ。
くるり:新たな挑戦、R&B/ヒップホップテイストを取り入れた進化
くるりはなぜこれまでR&B/ヒップホップを避けてきたのか?
ルーツや音楽シーンの影響
くるりの音楽は、これまで独自のスタイルを確立してきた印象がありますが、新たな挑戦は、今後の活動にも大きな影響を与えそうです。
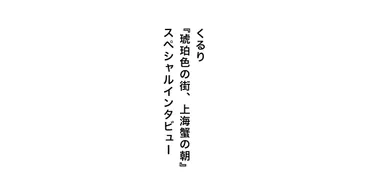
✅ くるりの最新シングル「琥珀色の街、上海蟹の朝」は、バンド結成20周年を記念して制作された楽曲で、R&B/ヒップホップ的なアプローチを取り入れたことが特徴です。
✅ これまで黒人音楽の影響を意図的に排除してきたくるりが、この楽曲で初めて黒人音楽的な要素を取り入れた背景には、20周年という節目を迎えたことと、新しい挑戦への意欲が挙げられます。
✅ 岸田繁は、黒人音楽を取り入れたことで、くるりの音楽の独自性を保ちつつ、新たな可能性を広げることができたと語っています。
さらに読む ⇒くるり『琥珀色の街、上海蟹の朝』スペシャルインタビュー出典/画像元: https://www.quruli.net/kohakushanghai_interview/くるりがR&B/ヒップホップを取り入れたことで、彼らの音楽に新たな可能性が生まれたと感じます。
今後の楽曲にも期待したいですね。
くるり結成20周年を記念したシングル『琥珀色の街、上海蟹の朝』は、これまで避けてきたR&B/ヒップホップテイストを全面的に取り入れた意欲作。
岸田繁は、バンド初期から黒人音楽の要素を排除してきた理由として、自身のルーツや当時の音楽シーンの影響を挙げ、くるり独自の音楽性を築き上げてきたことを説明。
佐藤征史も、他のバンドと差別化を図るため、黒人音楽の模倣は避け、独自の音楽性を追求してきたと語る。
しかし、20周年を迎え新曲制作の際に、これまでとは異なるアプローチを試みようと、R&B/ヒップホップの要素を取り入れ、新鮮なサウンドを生み出した。
楽曲における新しい試みは、くるりの音楽的可能性を示すものであり、今後の活動にも期待が高まる。
え、くるりって、R&Bとかもやるん?意外!でも、なんかめっちゃかっこいいやん!
くるり:音楽への探求心と進化するライブパフォーマンス
くるりの岸田繁は、どんな音楽的特徴で知られていますか?
独特の「間」とテンポ感
くるりの音楽は、常に進化を続けており、彼らの音楽への探求心は、多くのファンを魅了しています。

✅ くるりの新曲「その線は水平線」は、岸田繁が以前から持っていたアイデアを元に制作された楽曲であり、バンド結成当初からの作り方で制作されたという。
✅ 今回の楽曲は、実験的な要素と歌モノ要素の2つの異なる方向性を持つ楽曲群の中に位置付けられ、従来のくるりが流行を取り入れていたスタイルとは異なり、楽曲に合わせた録り方を重視した制作プロセスで制作された。
✅ 岸田繁は、デジタル機器の進歩によって容易に音作りができる時代になった一方で、実際に音を生み出すには機材の選択や使用方法が重要であることに改めて気づき、楽曲制作における新しい発見を得たことを語っている。
さらに読む ⇒ムジカ出典/画像元: http://musica-net.jp/articles/preview/6819/岸田繁さんのクラシック音楽への造詣の深さや、ライブパフォーマンスにおける新たな試みは、くるりの音楽に対する熱意を感じさせます。
くるりの岸田繁は、自身の音楽活動における広がりや、クラシック音楽への深い関心を語った。
彼は音楽を聴く際、文脈にとらわれず、様々なジャンルの音楽を繋ぎ合わせて聴くことを好み、シューマンからラッツ&スターへ繋がるような独特な音楽体験を重視する。
また、ウィーン交響楽団のパーカッショニスト、フリップ・フィリップとの出会いをきっかけに、クラシック音楽に対する考え方が大きく変わったという。
フィリップの革新的なスコアから刺激を受け、クラシック音楽への理解を深め、現代音楽や民族音楽にも造詣が深い彼から多くの影響を受けた。
岸田は、ロックミュージシャンでありながらクラシック音楽への情熱を持ち、交響曲という新たな表現に挑戦している。
幼い頃からゲーム音楽に影響を受け、特に「ドラゴンクエスト」の音楽がクラシック音楽への興味を育んだと語る。
岸田は、ロックとクラシックという異なるジャンルを繋ぎ、独自の音楽世界を創造し続けている。
くるりが新作EP『愛の太陽EP』をリリース。
前作「天才の愛」からの揺り戻しのようなストレートなポップネスが光る作品となっている。
ベーシスト佐藤征史へのインタビューでは、前作リリース後の2年間、ライブ活動が中心となり、オンラインでのライブを通してバンドとしての新たな軸が見えたと語った。
従来のくるりのライブはサポートメンバーを必要とするため活動の腰が重く、事前にアレンジなどを詰めてからツアーを行うことが多かったが、オンラインライブではリハ1日という限られた時間の中で、その場のノリで演奏する楽しさを再認識したという。
また、25周年記念公演『くるりの25回転』ではこれまでの作品への感謝を込めて、満遍なく曲を演奏したと振り返った。
くるりは2018年2月21日にシングル『その線は水平線』をリリースする。
この曲は、2010年のアルバム『言葉にならない、笑顔を見せてくれよ』のレコーディング時から存在していたが、アルバムの曲との立ち位置や、くるりらしさの追求という理由からリリースが延期されていた。
8年の歳月を経て、ドラムに屋敷豪太を迎えることで完成にこぎつけた。
佐藤征史は、くるりの特徴について「テンポ」が重要な要素だと語る。
他のバンドと比べてテンポがゆっくりで、メロディーも長い小節をかけて一周することが多いため、独特の「間」が生まれていると説明する。
この「間」は、くるりらしい「もっさり感」を生み出し、他のバンドでは真似できない個性的なサウンドを作り出している。
『その線は水平線』は、近年のくるりの楽曲とは少し毛色が違う仕上がりとなっている。
しかし、そこにはくるりらしさ、つまり「目の前に広がる道系」とも呼ばれる、くるりならではの独特の「間」とテンポ感、そして「もっさり感」がしっかりと存在する。
この楽曲は、くるりの王道を行くミディアムテンポのロックナンバーであり、ファン待望の作品と言えるだろう。
くるりの音楽って、なんか深いわ。私も、もっと音楽について勉強したい!
くるりは、オリジナルメンバー再集結による新作アルバムや映画公開、そして音楽への新たな挑戦など、精力的に活動しています。
今後も彼らの進化を見守っていきたいですね。
💡 くるりのオリジナルメンバー3人による楽曲制作を追ったドキュメンタリー映画『くるりのえいが』が公開
💡 くるりの最新アルバム『感覚は道標』は、オリジナルメンバー3人による制作
💡 くるりは、R&B/ヒップホップテイストを取り入れた楽曲を発表し、音楽の幅を広げている


