平安時代の結婚事情!『光る君へ』ドラマと史実を比較してみた?妻問婚から摂関政治まで、平安時代の結婚制度とは!?

💡 平安時代の結婚は、現代とは大きく異なっていた
💡 妻問婚という制度が存在していた
💡 藤原氏による摂関政治が成立した背景には、妻問婚があった
それでは、平安時代の結婚制度について、詳しく見ていきましょう。
妻問婚と摂関政治
それでは、妻問婚について詳しく見ていきましょう。
公開日:2021/11/21

✅ 妻問婚は、古代日本で流行った結婚スタイルで、夫と妻は別居し、夫が定期的に妻の家に通うというものでした。
✅ 妻問婚は、縄文時代の集団生活における出会いの問題から生まれたと考えられており、その後、弥生時代の稲作開始による集落の拡大と人口増加にもかかわらず、そのスタイルが受け継がれました。
✅ 妻問婚では、男性は女性に和歌で求婚し、結婚の儀式は三日間の通いによって行われました。子育ては母親の実家で、母親の実家の長が強い影響力を持つことから、藤原氏が天皇の母親の親戚となり、摂関政治へと発展していきました。
さらに読む ⇒まなれきドットコム出典/画像元: https://manareki.com/tumadoikonなるほど、妻問婚が摂関政治へと発展していったという流れは、現代では考えられないですね。
平安時代以前、妻問婚と呼ばれる結婚形態が一般的で、夫は妻の実家に通って同衾し、妻の実家が権力を持っている場合や、妻が夫よりも身分が高い場合に多く行われていました。
妻問婚は、縄文時代の集団生活の中で、若い男女が出会い結婚相手を見つけるために生まれたスタイルが起源と言われています。
妻問婚では、男性が意中の女性に和歌を送って求愛し、女性は和歌で返信して承諾を示します。
数回の手紙をやり取りした後、夜に男性が女性の元を訪れて同衾し、朝が来る前に自分の家に帰ります。
3日間連続で通った後に結婚の儀式を行い、正式に結婚が認められました。
妻問婚では、子供が生まれると母親の実家で育児が行われ、家長が最も発言権を持ちました。
この子育て事情を利用して、藤原氏が天皇の母親の親戚(外戚)となって政治の実権を握ったのが摂関政治です。
外祖父が摂政となり、皇族以外の者が天皇を補佐することで、藤原氏が政治の実権を握りました。
そうやな、現代の結婚とは全然違うんやな。
平安時代の婚姻形態
平安時代の婚姻形態は、現代とは大きく異なる点が多いですね。
公開日:2024/03/24

✅ 藤原道長は、一条天皇の即位式で高御座に置かれた生首を発見する場面に遭遇し、藤原兼家の指示で騒動を隠蔽した。
✅ ドラマでは、花山院が呪文のようなものを唱えるシーンが描かれたが、これは密教系の仏教で信仰されている大威徳明王への真言であり、悪縁を断ち切るための祈祷であった。
✅ 道長がまひろに「妻になってほしい」とプロポーズするシーンでは、まひろが北の方(正室)にしてくれるのかと尋ね、道長の沈黙から平安時代の婚姻制度において、正室と妾の区別が厳格であったことが示唆された。
さらに読む ⇒日刊サイゾー出典/画像元: https://www.cyzo.com/2024/03/post_364540_entry.html平安時代の婚姻制度は複雑で、現代の私たちには理解しにくい部分も多いですね。
平安時代の婚姻形態は、法的には一夫一妻制でしたが、実際には一夫多妻制でした。
男性は正妻の他に妾を持つことが一般的でしたが、正妻と妾の身分には大きな差がありました。
正妻は法的に守られ、妾は男性の気持ち一つで捨てられる可能性がありました。
結婚までのプロセスは、男性が女性に和歌を送ることから始まります。
女性が和歌に興味を示せば、男性は3日間連続で女性の元を訪れ、3日目に寝室で「三日夜餅」を共に食べます。
その後、披露宴が行われ、結婚が正式に認められました。
この結婚形態は、女性にとって不利なものでした。
妾は法的な根拠がなく、男性の気持ち一つで捨てられる可能性がありました。
一方、正妻は法的に守られていましたが、それでも男性の不倫を阻止することはできませんでした。
平安時代は、男は女をたくさん持てたんじゃ。でも、正妻と妾の区別は厳しかったらしいわよ。
『源氏物語』における婚姻
『源氏物語』は、平安時代の恋愛と結婚を描いた作品として有名ですね。

✅ 光源氏は、理想の女性である紫の上を愛していましたが、彼女には家柄と子供がいませんでした。当時の貴族社会では、家柄と子供は女性にとって必須であり、紫の上は光源氏からの愛情だけで生きる脆弱な立場にありました。
✅ 一方、光源氏は准太上天皇としてあらゆる栄華を極めていましたが、唯一欠けていたのは「我が身分に相応しい正室」でした。そこで光源氏は、内親王である女三宮を正室に迎えますが、それは紫の上が傷つくことを意味していました。
✅ 光源氏は女三宮を藤壺の面影を持つ女性として愛していましたが、実際には藤壺とは似ても似つかず、幼くて女性として見ることができませんでした。光源氏は紫の上への愛情よりも、藤壺への憧れから女三宮を選び、紫の上は光源氏に見られていたのは「自分」ではなく「藤壺の面影」だと気づき、心を傷つけられます。
さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン - Japaaan出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/133216『源氏物語』は、平安時代の恋愛と結婚観が複雑に描かれている作品ですね。
『源氏物語』では、「妻」を表す用語が明確に区別されておらず、妻妾の区別も明確ではありませんでした。
正妻は、同居や儀式婚、初妻であることが絶対条件ではなく、所生子や後見・愛情などをも含めた様々な条件により事後的に決定されました。
『源氏物語』の紫の上の妻の座については、正妻説・妾妻説の両説に根拠がありますが、どちらの説も決定的なものではありません。
紫の上の地位は、物語の文脈から切り離して婚姻制度の観点のみで裁断すべきではないでしょう。
物語作品では、居住形態が物語の論理と関連しています。
『源氏物語』では、「据ゑ」の用語が独自の用法で用いられ、後見のない我が身に苦悩する女君の姿が描かれます。
また、「対」と称される女君は、妻妾同居という虚構的な居住形態が設定された物語で、その両価的な立場を示唆する呼称として用いられます。
『源氏物語』の一夫多妻制については、一夫一妻制説が提出されていますが、物語を史料として婚姻制度を解明することは有効ではありません。
物語の婚姻形態は、物語の展開上いかなる仕組みとして働いているのかを考察する必要があります。
紫の上、かわいそう。光源氏って、ほんまに女たらしやな。
平安時代の婚姻慣習の研究
平安時代の婚姻制度を研究することは、当時の社会構造を理解する上で非常に重要なことですね。
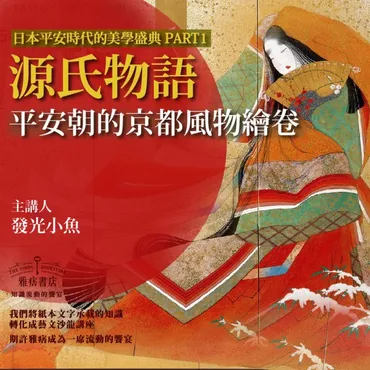
✅ 「源氏物語」を題材に、平安時代の京都を舞台にした風物絵巻を語る講座。
✅ 京都の史跡や風習を「源氏物語」のストーリーと絡めて紹介し、平安時代の世界観を体感できる。
✅ 講師は文史旅行作家「発光小魚」氏。平安時代の貴族文化、文学、歴史、そして「源氏物語」の魅力をわかりやすく解説する。
さらに読む ⇒雅痞書店 - 藝文沙龍出典/画像元: https://online.yup.com.tw/20220224平安時代の婚姻制度を、文学を通して分析するというのは、新しい視点ですね。
平安時代の婚姻制度の実態は十分に解明されていません。
本研究では、『源氏物語』に描かれている婚姻制度を分析することで、その実態を解明しようとしています。
平安時代には、大勢の妻たちの序列、正妻の条件、結婚に至る手順、恋愛と結婚の区別など、婚姻制度に関する疑問が数多くありました。
本研究では、これらの疑問に文学研究の立場からアプローチし、婚姻制度を踏まえた物語の分析を行います。
それにより、フィクションである物語ならではの独自性や仕組みを見いだし、作品の魅力を浮かび上がらせることが最終目標です。
本研究により、婚姻制度の混乱の整理にもつながると期待されています。
平安時代のことは、よく知らんけど、源氏物語は面白そうだね。
奈良時代の妻問婚
奈良時代の妻問婚は、平安時代の婚姻制度に影響を与えたと考えられています。
公開日:2024/03/28

✅ 平安時代の結婚は現代とは大きく異なり、婿入りは現代で言うところの「結婚」とは異なる形式であり、当時の習慣に基づいて考えると藤原道長と源倫子の結婚はスムーズに進んだとは言い切れない部分があったことがわかります。
✅ 平安時代の結婚は、現代のような恋愛結婚ではなく、政治的な側面が強く、特に女性は家柄や資産によってその運命が決まることが多く、愛や相性よりも資産が重視されたことがわかります。
✅ 記事では「光る君へ」のドラマと史実を比較しながら、平安時代の結婚事情について解説されており、当時の結婚における儀式や慣習、特に「後朝(きぬぎぬ)の文」や「三日夜(みかよ)の餅」などの重要性が解説されています。
さらに読む ⇒ BUSHOO!JAPAN(武将ジャパン)出典/画像元: https://bushoojapan.com/jphistory/kodai/2024/03/28/180738平安時代の結婚は、現代とは全く違うものだったんですね。
奈良時代にも妻問婚が行われており、夫が妻のもとに通って妻が寝床や食事を用意していました。
男性は妻の生理がきていないことを確認してから訪問日を告げ、当日には先駆の使者を走らせていました。
妻問婚は、夫婦が同居せず、男性が女性のもとに通うという結婚形態で、現代の結婚とは大きく異なっていました。
また、奈良時代には母系氏族制が続いており、母系氏族制の始まりは、村内婚による母系家族でした。
奈良時代も、平安時代も、結婚は難しいものだったのよ。
平安時代の婚姻制度は、現代の私たちにとって、非常に興味深いものですね。
💡 平安時代の婚姻形態は、一夫多妻制が主流だった
💡 妻問婚は、平安時代の婚姻制度の中で重要な位置を占めていた
💡 『源氏物語』は、平安時代の婚姻制度を反映した作品


