『自己肯定感』って何?精神科医 泉谷閑示氏が語る心の健康問題とは?泉谷閑示氏が語る自己肯定感と現代社会の問題点
「自分が嫌い」と感じるあなたへ。精神科医・泉谷閑示氏が、自己肯定感の低さの原因を解き明かす!幼少期の「いや」を言えない環境、親の言動が、自己不信を生み出すメカニズムとは?核家族化による育児負担、第三の反抗期の重要性、そして「自分のしたいこと」を見つけるヒントがここに。泉谷氏の臨床経験と、豊富なメディア出演が裏付ける、現代社会を生き抜くための自己分析と、心の処方箋。
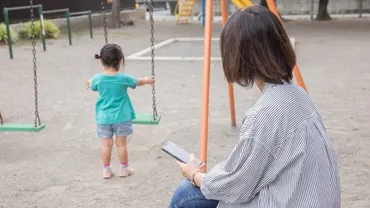
💡 自己肯定感の重要性と、それが低い場合に生じる生きづらさについて解説します。
💡 幼少期の親との関係が、自己肯定感に与える影響について掘り下げていきます。
💡 泉谷閑示氏が提唱する、自己肯定感を高めるための方法論を紹介します。
では、自己肯定感と現代社会が抱える問題について、泉谷先生の見解を深掘りしていきましょう。
現代社会と自己肯定感の危機
自己肯定感低下、なぜ?泉谷氏が指摘する原因は?
過度な習い事と、親の言動。
自己肯定感の低さの原因は、幼少期の親との関係にあるという泉谷先生の見解は、非常に興味深いですね。
公開日:2025/07/01
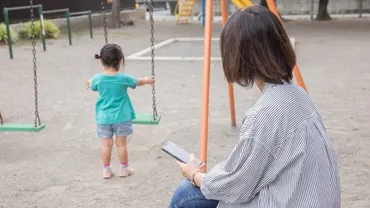
✅ 自己否定的な感情の原因は、幼少期の育ち方にあると精神科医の泉谷閑示先生は指摘している。
✅ 子どもは親を「ほぼ神」のような存在として全幅の信頼を寄せるが、親は不完全な存在であるため、子どもに対して問題のある接し方をしてしまうことがある。
✅ 思春期に親への批判的視点が芽生えるものの、既に子どもの人格の基礎部分には親の影響が強く残ってしまっている。
さらに読む ⇒婦人公論.jp|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/17568?display=full親の接し方が子どもの人格形成に深く関わっているという指摘は、多くの親にとって耳の痛い話かもしれません。
核家族化が進む現代において、より一層、育児に対する意識を高める必要がありそうです。
精神科医の泉谷閑示氏は、最新刊『「自分が嫌い」という病』において、現代人が抱える自己肯定感の欠如という問題に焦点を当て、その原因を分析しています。
本書では、過度な教育熱心さから子どもたちが多くの習い事を強いられ、「やめたい」と言う気持ちを親が安易に禁じてしまう現状を問題視しています。
これは、子どもの主体性を奪い、自己肯定感を低下させる要因の一つとして指摘されています。
泉谷氏は、幼少期の育ち方が自己肯定感の形成に大きく影響すると述べており、親の言動が子どもの人格形成に深く関わっていると分析しています。
特に現代の核家族においては、育児負担が親に集中しやすく、親の未熟さや偏りが子どもに直接的に影響を与えやすい状況にあると指摘しています。
えー、なんか、親が神様って感覚、めっちゃわかるー!でも、親も人間やからなー、難しいよなー!
「いや」を言えることの重要性
反抗は成長の鍵?「第三の反抗期」って何?
自己肯定感を育む、大人に必要な反抗です。
フロムの言葉を引用し、人間の精神的発達には「いや」を言える反抗の経験が不可欠というのは、深いですね。

✅ 精神科医の泉谷閑示氏が、現代の精神科治療の問題点と、患者の根本原因を探る診察について語った。
✅ 現代の患者はエネルギーが低く、親離れ子離れできていないケースが多いと指摘し、真の成熟には反抗期が不可欠であると説いた。
✅ 情報過多な社会で憧れが持ちにくくなっていることや、ニーチェの「三様の変化」を例に、精神の成熟過程を解説した。
さらに読む ⇒GOETHEゲーテ出典/画像元: https://goetheweb.jp/person/article/20240905-kishi-izumiyaイヤイヤ期、思春期、そして成人後の第三の反抗期、この三つが精神的成長に不可欠だという点は、非常に興味深いですね。
子どもの「いや」を受け止めることの重要性が理解できます。
泉谷氏は、フロムの言葉を引用し、人間の精神的発達には「いや」を言える反抗の経験が不可欠であると強調しています。
具体的には、2~3歳のイヤイヤ期、思春期の反抗期に加え、成人後の「第三の反抗期」の重要性を説いています。
幼少期に「いや」を言えなかった子どもたちは、自分の気持ちを抑圧し、自己不信に陥りやすいと指摘しています。
泉谷氏は、子どもたちが「いや」を言えない環境は、結果的に自分の感情を理解できなくなり、「自分が嫌い」という感情に繋がると警鐘を鳴らしています。
いやー、俺も昔は親に『いや』って言えんかったなー。今思えば、もっと我慢せずに生きてりゃよかったわー! ま、今からでも遅くないけどね!
次のページを読む ⇒
「自分のしたいことが分からない」若者の増加に着目。幼少期の経験が自己肯定感に影響。泉谷氏が臨床経験と多方面での活動を通して、現代社会における生き方を考察します。

